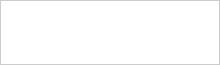経緯
発達障害者支援法(平成17年4月)の施行を受け、川崎市では平成18年5月に発達障害者支援体制整備検討委員会を設置し、支援センターについては『川崎市に必要なものは医療相談機能を備えた機関ネットワーク型のセンターである』とのコンセプトを明確にして、平成19年2月、支援センター運営法人公募が実施されました。法人が受託先に決定し、平成20年1月に「川崎市発達相談支援センター」が開所しました。
支援センターは川崎市内の発達障害児・者の支援拠点として、川崎駅東口から徒歩10分の民間ビル内に医師相談室・相談室・プレイルーム等を備えています。
保健・福祉・医療・教育・労働の各分野から多面的、重層的な支援、乳幼児期・学齢期・成人期の各ライフステージに合わせた『発達障害者と家族のための相談機関』としての機能が果たせる組織と運営システムづくりを目標に、医師・ケースワーカー・心理士等のスタッフを配置しております。
また、発達障害児・者支援の特徴とも言える広範囲な業務領域に対応するために機関連携を重視しながら業務を進めています。
事業展開の方針
支援センターの相談活動は、下の表に示した機能と枠組みを常に意識して行い、日常業務にメリハリをつけて取り組むようにしています。
しかし、現実的には各相談機能の境目は必ずしも明確ではないことから、ニーズに沿って動く相談現場として次のような段階に分けて実施しています。
(1)1次的相談:1回の電話や面接で解決、あるいは2次的相談に及ばなかったもの
(2)2次的相談:面接を複数回実施し、問題解決のパートナーの役割を担ったもの
(3)3次的相談:支援者からの相談に乗り、解決までの責任の一端を担ったもの
なお、アセスメントや適切な他機関紹介は、発達障害の特性を配慮した相談抜きには進まないことが多く、現状では2次的相談の割合が高くなっています。