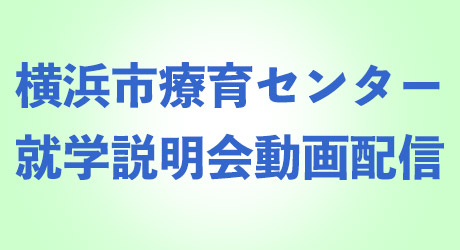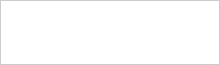横浜市南部地域療育センター所長の礒﨑仁太郎です。

はじめまして。令和2年4月より横浜市南部地域療育センターの所長を務めております、礒﨑仁太郎と申します。よろしくお願いいたします。
当センターの名前にある『療育』という言葉は、あまりなじみのない言葉かもしれません。辞書によれば『療育』とは「治療をしながら育てること」とあります。「治療をする」と言われると、なんだかものものしい感じがします。また「何か悪いところがあるのでそこを治さなければいけない」という気持ちにさせられ、居心地が悪い気がします。
そもそも子育てとは、その子らしさが存分に発揮されるように、周りが応援していくことだと思います。周囲の応援を受けて、赤ん坊や幼児は新しいことに挑戦します。そうして徐々に自分でできることを増やしていき、その成果に手ごたえを感じ、自信を深めていきます。その自信が新たな課題に挑戦する意欲を生む、というサイクルを繰り返します。これは乳幼児に限らず、青年期も老年にかけてでも同じです。これが「発達」とか「成長」と呼ばれる過程です。
「成長」に関していえば、順風満帆に事が運ぶとは限りません。子どもの挑戦がうまくいかないことがあります。直面した課題がなかなか乗り越えられない時があります。本人も周りももどかしく、時に疲弊を強めます。この状況の多くは本人と課題とのミスマッチによります。このミスマッチをどう乗り越えるのか、が子育ての要所となります。ミスマッチの理由が本人の徳目や個性に由来することがあります。「発達の障害」はそのうちの一つです。
「発達の障害」を抱えた子どもの子育てにはコツや工夫が必要です。この子育てのコツや工夫のために、医療の知識が有効なことがあります。「子どもの心や頭の中ではどんなことが起こっているのか」の知見を子育てに生かす、つまり「医療の知見を子育てに生かし、その子が自分らしく成長する」ということです。医療の「治療」の部分よりも「知恵」の部分を大いに利用したいとするものです。私は『療育』をそんな風に考えています。
我々の横浜市南部地域療育センターは市内で最も古く、歴史のある療育センターです。歴史がある、ということは、これまでに利用された方々からの知恵や工夫が蓄積されているということです。私は先日赴任したばかりですので、このような先人たちからの贈り物をお預かりしていることを心強く思っております。そしてそれを皆様と共有できることを心掛けたいと思います。
私のことを外来や待合室で見かけることがあろうかと思います。トッポジージョに似た医師が私です。お気軽にお声がけいただければ嬉しく思います。
礒﨑仁太郎